『ショパン』2024年6月号p.66-67より
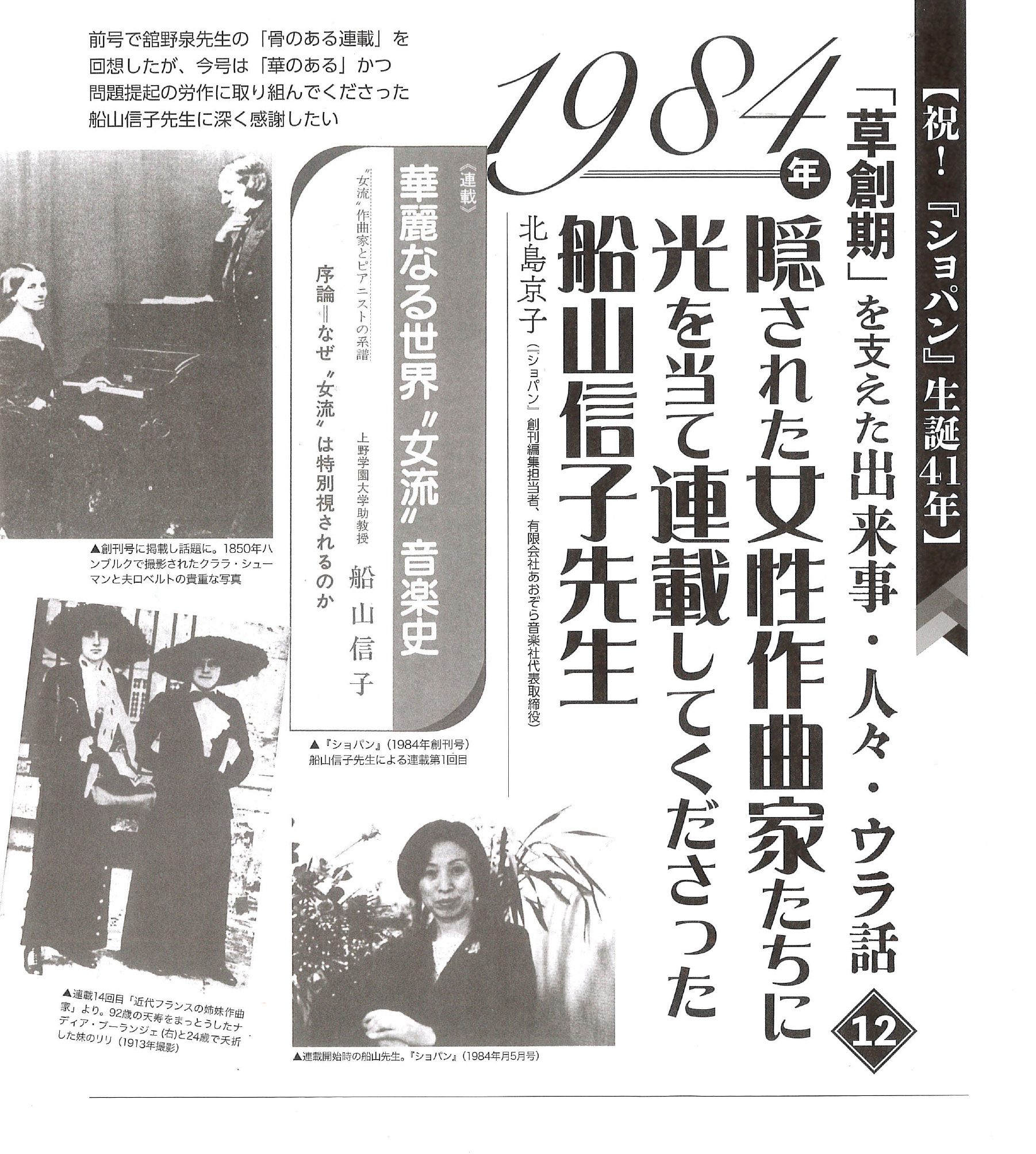

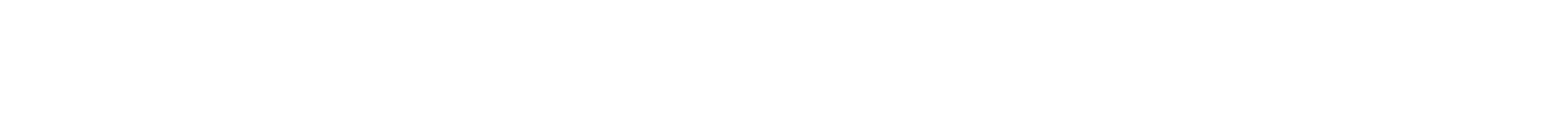
あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。
以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。
『ショパン』2024年6月号p.66-67より
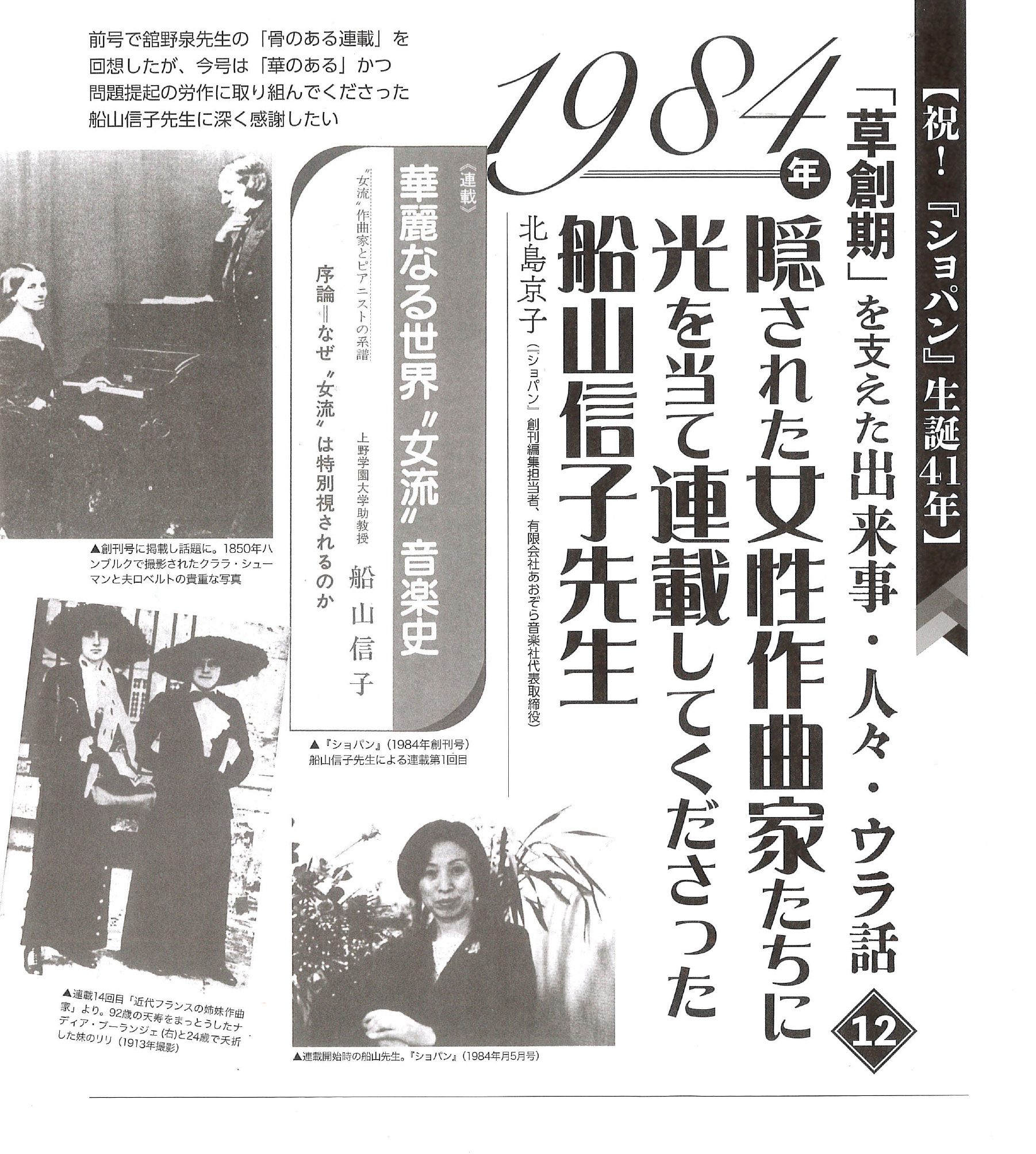
前号で舘野泉先生の「骨のある連載」を
回想したが、今号は「華のある」かつ
問題提起の労作に取り組んでくださった
船山信子先生に深く感謝したい

前号の本記事で、舘野泉先生の原稿をヘルシンキから東京まで「伝書鳩」として運んでくださったフィンランド航空の「客室乗務員」を、私は原稿で当時の呼称の「スチュワーデス」と記載し、編集部が現在の正しい名称に訂正してくださった。確かにスチュワーデスは死語である。この4月JAL日本航空において、客室乗務員出身の初の女性社長が誕生している。かつてスチュワーデスの多くは結婚や出産後も働き続けることはできなかったが、今は違う。性差を超えて能力を活かせる時代だ。
ただしバブル景気以前の『ショパン』創刊の1984年、今ほど海外旅行が大衆化されていなかった時代のスチュワーデスは、外国語が使え、海外を行き来できる高いステータスの、しかも身長・容姿の基準をパスし森英恵デザインの制服が似合うような女性がなれるとされていた。最難関の憧れの女性職業だったが、離職率も高かった。
時代が変わり、国連総会で決めた「女子差別撤廃条約」や国内の「男女雇用機会均等法」の効力が広まるにつれ、客室乗務員はハードな職業という認識も高まった。機内の立ち仕事の労働環境から昨今ではヒールのパンプスを脱ぎスニーカーを履くようになったし、契約社員の客室乗務員も増えた。40年前とは隔世の感がある。
「女医」、「女史」、「女流作家」と言われなくなったのは、それだけ女性の実力と社会認知が行きわたったからだ。創造や専門技能の場が男性の占有物と認知されていた時代には、「女流」と言われなければならなかった。が今、音楽大学の学生の9割は女性で、作曲科の学生も女性が過半数だ。音楽界における意識は変化しているのか?
現在、オケのコンサートマスターが女性の場合「コンサートミストレス」と呼称されるが、これは差別ではなく親しみある敬称のように聞こえる。言葉は、使われる場での人間関係によって受けとめられるのだろう。
さて時は1983年8月の創刊準備会議。内藤編集長(1927~2018)は得意満面で提案した。「これ、まだどこもやってないだろう」。船山信子先生による女流作曲家の連載企画だった。「ええ~っ! 女流作曲家ってマイナーじゃありませんか」と編集部。以前から内藤社長は金井喜久子、吉田隆子といった作曲家を評価していた。「社長好みの「大正ロマン」に陥るのでは・・・」と私。「どっこい、対象は世界の女流作曲家だ!」と内藤編集長。「えっ海外の女の作曲家って、乙女の祈りのバダジェフスカと六人組の紅一点タイユフェールくらいでしょう!」と驚く編集部。「そうだろう、みんなその程度の認識だ。だから船山先生のご登場だ!」と、確信を持って推す社長。
創刊号から始まった「華麗なる世界〝女流〟音楽史」。内藤編集長は「〝女流〟という表記が大事だ。こうしないと問題提起にならないからな」と。「え、そんな意図なの」と驚く編集部。第1回の「序論=なぜ〝女流〟は特別視されるのか」は、執筆の動機と今後の展望を知らせる興味深い考察だった。
中で明かしているが、この連載の水先案内をしてくれることになるのが『女性作曲家の国際エンサイクロペディア International Encyclopedia of Woman Composers』(第1版1981年、 Bowker社刊)という、紀元前から現代まで何と70ヵ国6,000人の女性作曲家が網羅されている大事典だった。そんなに大勢の女性作曲家が現存していたのに、なぜこれまで光が当たらなかったのか、誰でも疑問が湧く。その解読・解説に船山先生はふさわしかった。文体は一見やんわりと淡々。しかし核心をえぐる筆鋒は鋭く明晰そのもの。外見は華奢で優雅だが船山先生その人を表す芯のある記事で、内藤社長がぞっこんになるのも無理なかった。
全16回の連載で、先生独自の選定により、紀元前の古代エジプトの歌姫で作曲家のイティから、レスビアンの語源となった古代ギリシャのレスボス島の作曲家サッポー、そして権威ある作曲賞のローマ大賞を受賞した現代日本の佐藤喜美氏まで、 20名以上の個性ある女性作曲家の光と影を取り上げた。毎回初めて知る話ばかりだった。
船山先生は最終回で「現代日本の女流作曲家については、いつの日か稿を改めたい」と記していた。これにより発奮した内藤編集長は、本誌の連載をもとに追加取材を加え補筆して、古今東西の女流作曲家の本『女性作曲家の系譜』を出そうと意気込んだ(たぶん1990年頃)。すでに何年も前に東京音楽社を退職してフリーランスになっていた私が呼び出され、編集担当を命じられた。
先生のご意向により日本の女性作曲家についての精確な資料収集をと、松島彜(まつしまつね)から田中カレンまで50人に(ご本人または著作権継承者に)調査書をお願いし、直接自筆の回答文書と作品の手稿譜など一次資料を送っていただいた。日本の女性作曲家を対象とした初めての調査で、貴重な資料の宝の山となった。
続いて船山先生は書き下ろしのためにパリに赴き、ベッツィ・ジョラスにインタビューし、さらにソ連の崩壊直後、タタールのソフィア・グバイドゥーリナを取材するという念の入れようだった。・・・が、当時の船山先生はご本業の教授生活が超多忙を極め、またその他要職を務める渦中で、執筆のための集中時間が取れず、ついに単行本の完成には至らなかった。日本の女性作曲家の資料は残念なことに返却している。
その後、船山先生は、女流作曲家で教育家として多くの優れた日本人弟子を輩出してきたアンリエット・ピュイグ=ロジェ氏の没後10年に、その人となりと業績を大著『ある「完全な音楽家」の肖像~マダム・ピュイグ=ロジェが日本に遺したもの』に編著者としてまとめ上げている(2003年、音楽之友社)。その中で、ピュイグ=ロジェ氏をたぐい稀な完璧な音楽家として屹立させるとともに(優れた様式や有能な弟子を遺しただけではなく)、彼女は日本においてひとつの楽派を創造したと喝破した。そこに心打たれた。点と点をつなげて線とし、面とし、豊かな音楽の水脈を育て楽派を創った一人の女性を書き著わした。ここに船山先生の「女流音楽史」連載時代から続いた(出版社は異なるが)一つの帰結点を見い出すことができ、溜飲が下がるのだった。
ちなみに、点と点で思い出すのは、本誌で好評連載中の「ピーター鈴木の横丁ばなし」の鈴木達也氏が、神奈川県立湘南高校・合唱部で船山先生の2年先輩にあたり、鈴木氏が歌曲「冬の旅」などを歌う時、また大学時代にも湘南仲間とカルテットを行なう時、いつも信子先生はピアノ伴奏を受け持ち、鈴木氏を「アニキ」と親しく呼んでいたと聞く。楽しそうなハーモニーが聞こえてくる話だ。