『ショパン』2024年5月号p.66-67より
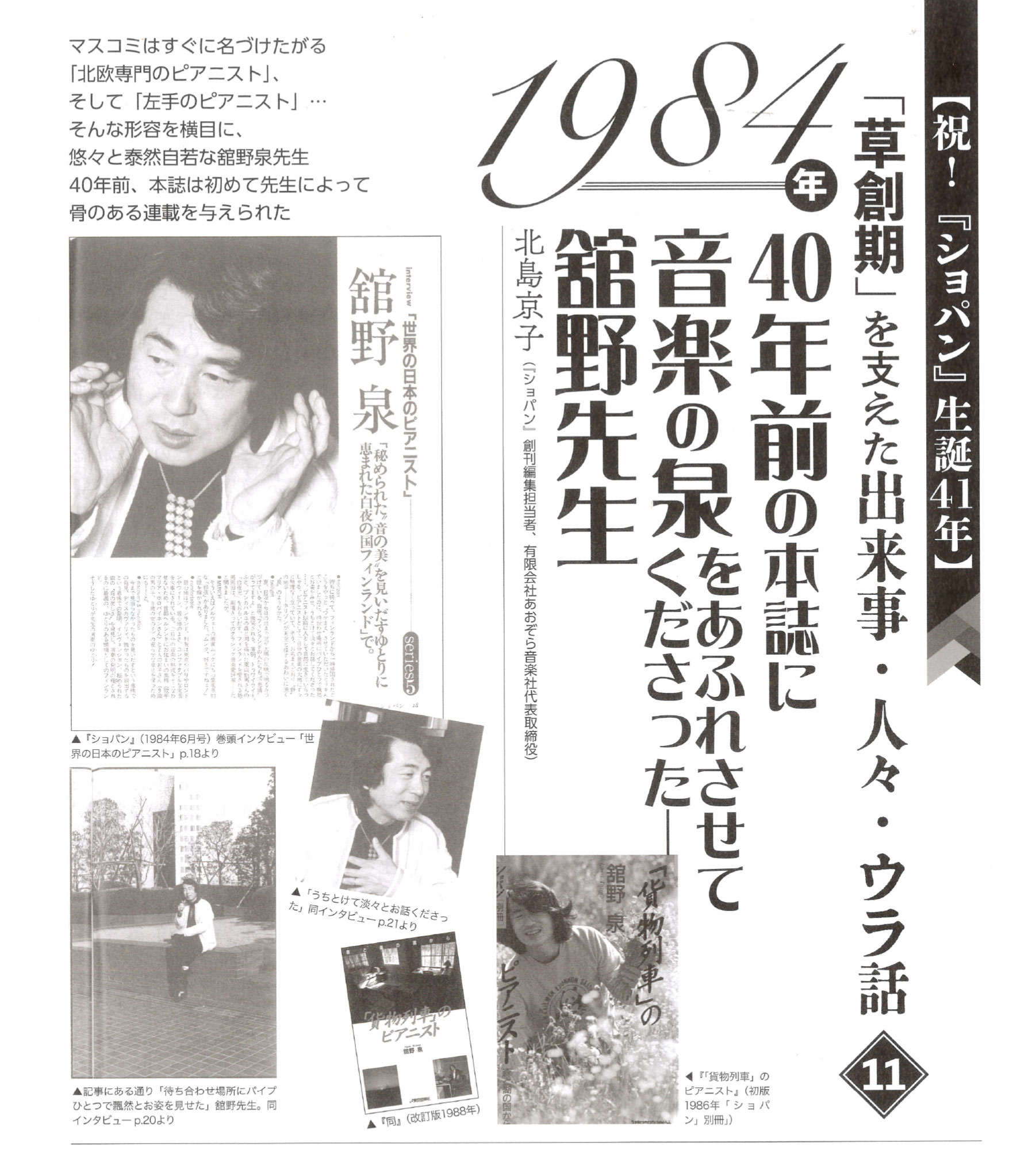

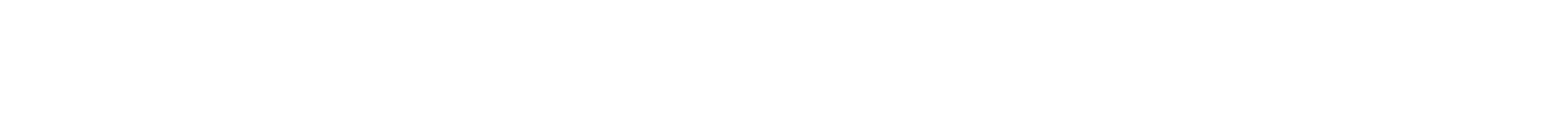
あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。
以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。
『ショパン』2024年5月号p.66-67より
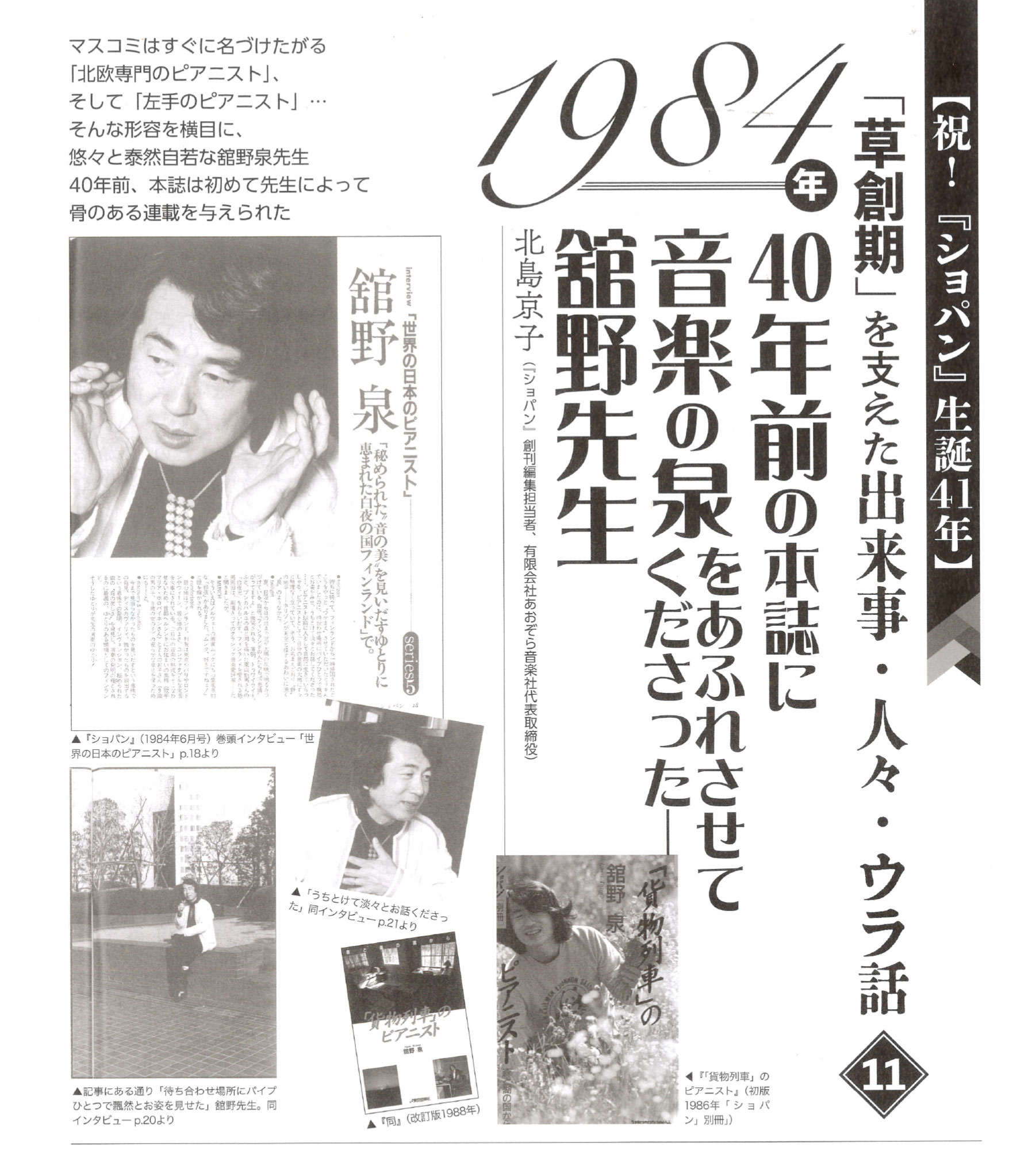
マスコミはすぐに名づけたがる
「北欧専門のピアニスト」、そして「左手のピアニスト」…
そんな形容を横目に、悠々と泰然自若な舘野泉先生
40年前、本誌は初めて先生によって骨のある連載を与えられた

『ショパン』では創刊から1年間、巻頭インタビュー「世界の日本のピアニスト」として12人のピアニストにご登場いただいた。トップページのタイトルと写真下には毎号、取材者によるピアニストの印象メモが5つほど綴られるのがお決まりだった。1984年6月号(創刊第5号)の舘野泉先生の印象の一つはこんなふうだ。
●horizon
待ちに待って、フィンランドから一時帰国されたところをやっと〝つかまえ〟させていただいたとリキんでいましたのに、待合せ場所にパイプひとつで飄然とお姿をみせ、うちとけて淡々とお話してくださった…。ピアニスト以前に人として自然に生きていらっしゃる。ピアニストとしてご自分の音楽の大地にすッと無理なく立っていて、そう、お名前どおり〝野〟の地平――ホリゾンが天空と接するあわいに湧く〝泉〟のようなかた。
この「地平と天空のあわいに湧く泉のようなかた」という印象は40年後の2024年の今も変わっていない。大地に根を張り、光に向かって音楽をあふれさせる泉。
時は1984年の蒸し暑い夏、編集会議が開かれ、内藤編集長(1927~2018)は、「創刊してやっと半年。これからが勝負だ!」と檄を飛ばすと、広告営業の担当、近藤茂さん(2023年8月号第3回を参照)が、「社長、ショパンはまだまだ無名の雑誌です。それなのに一部では『ショパンって、あの軽薄短小な雑誌ね』とそんな声は広まっているんですよ。流行を追うのではなく、骨のある企画を考えてください」。すると内藤編集長は目前の6月号を手に取り、舘野先生インタビューを見て言い放った。「よし、舘野さんに連載執筆を頼もう。舘野さんは文学青年で女性ファンも多いことだし…」と。
「社長、記事をちゃんと読んでください。舘野先生は社長の好きな青白い文学青年じゃありません!もっと野太い行動派の生活人です!言葉には品格がありますが…」と私。「理屈はいいから、連載を取って来い!」と内藤編集長。「ウチのような無名の雑誌に書いていただけるでしょうか?」と不安な編集部。
結局、内藤社長は、世界各地に演奏旅行で超多忙のフィンランドに住む舘野先生を何とかクドき落とし、「連載をご快諾してくださった」と満悦の体。半年後の1985年1月号から「舘野泉のフィンランド便り」の連載が開始された。私は原稿受取りの担当となった。
律儀な舘野先生は、決して締め切りに遅れることなく、毎回、万年筆の手書き原稿とたくさんの譜例が入ったズシリと重いエアメールを送ってくださった。内容は実に手ごたえがあった。
フィンランド独自の歴史と社会、自然。それが音楽にどんな影響をもたらすのか、他の北欧とどう違うのか、フィンランドの音楽の深さについて面白く伝えてくださった。単にフィンランドに居住するピアニストではない、身体の奥深くに燃える音楽の精髄を伝えてくださる熱量に圧倒された。読者からも、重厚なのに面白いと大好評だった。
ある時、編集部に電話があった。「舘野先生からお原稿をお預かりしていますので、渋谷までお届けします」と言うではないか。フィンランド航空の日本人スチュワーデスだった。(ヘルシンキ~成田の直行便が開通したのは、たった1年前の1983年)。ヘルシンキから直接手に持って原稿を運んでくださったその美しい「伝書鳩」スチュワーデスさんは、微笑みながら告げた。「舘野先生の書かれたもの、いつも楽しみに読んでますよ」。恐縮しきり。
精緻な原稿にさらに念を入れ、舘野先生はフィンランド語の表記や伝統文化について、この人を訪ねるようにと指示をくださった。それがフィンランド文化研究家の稲垣美晴氏という美しい人で、素人の私どもに優しく教示してくださった。(稲垣氏は、ハンヌ・イラリ ランピラ『シベリウスの生涯』を舘野先生の監修のもと翻訳している。著書『フィンランド語は猫の言葉』も有名で、現在はフィンランド文化を伝える出版社「猫の言葉社」の代表である。)
温かく誠実なお人柄の舘野先生の周りには、優雅な女性応援団が多かった。
連載開始時から「早く単行本化して」という読者の声が高かった。しかし私は、単行本化を見ることなく、連載担当第5回を最後に東京音楽社を退社した。その後任は内藤社長が引き継いだ。そして連載が面白く発展したのは私が辞めた後の第7回目からだった。
連載13回までをまとめ、写真も豊富に収録して「ショパン別冊」として単行本化された際、舘野先生は「まえがき」にこう記した。「いささか真面目な調子でスタートした『フィンランド便り』は第7回を迎えて突然変貌し、「北欧に住む日本人ピアニストのエッセイ」という形をとりはじめる。その変貌ぶりは、長く暗い冬の後で、ある日突然春が来て新緑と花の海となり、きびすを接して夏がやってくる、まさに北欧的な季節の変容と、無意識のうちにみごとに呼応したものだった」と。この変貌によって舘野先生の本領は発揮され、「名エッセイ」が誕生した。
表紙の装幀で、デザイナーの光本順一氏(2024年2月号第9回参照)と内藤社長がデザインについて侃侃諤諤やり合っているのを、舘野先生は口をはさまず穏やかに横から見ていらしたと聞く。「制作スタッフの皆様との熱のこもった討論も「産みの楽しさ」として忘れがたい」と綴っている。これ以上の優しさはない。
その後も『「貨物列車」のピアニスト』は1988年に「改訂版」、さらに2015年に「新装版」と版を重ね、連載開始より40年、今や数ある舘野先生の数々の刊行著書の中で、異色を放つ、それでいて枯れることのない音楽の源泉をすくいあげた処女本となった。舘野先生ありがとうございました。