『ショパン』2023年10月号p.68-69より


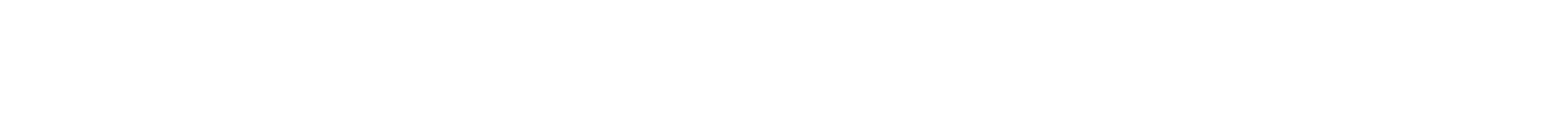
あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。
以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。
『ショパン』2023年10月号p.68-69より

編集長・内藤克洋(よしひろ)には生涯の友人がいた。
内藤の雑誌創刊時にはいつも助っ人として現れ、陰で支え、風のように去って行った。
その名は岩崎呉夫(くれお)(注1)。辣腕(らつわん)編集者だった。

創刊号が出て1984年が明けた。新年から間もなくすると、その年の来日ピアニストの予定が発表される。今年はどんなピアニストが来るのか、その顔ぶれにワクワクしながら来日ラインナップを作成する楽しみは、39年前も今も同じだ。
「アルゲリッチが来る!」 編集部がどよめいた。まだ10ヵ月も先の秋の話で、今回が決して初来日ではない。しかし『ショパン』にとっては「事件」だ。アルゲリッチは当時42歳。きらめく才をほとばしらせ疾走していた20代の「鍵盤の女神」は、豊かに成熟し名実ともに「ピアノ界の女王」として君臨していた。
「よし! 秋の来日まで、連続して毎号アルゲリッチを取り上げるぞ!」と即決。1984年4月号に「アルゲリッチ来日・第1報」、5月号に「第2報」、6月号に「第3報」と特別ワクを組み、毎号アルゲリッチの演奏論と人間論をさまざまな執筆陣に寄稿してもらった。
当時はソリストとしての絶頂期だった(後に振り返ると、この1984年を境に、アルゲリッチはソロからアンサンブルへと活動をシフトさせていった)。今回の来日ではソロリサイタルの他、初披露となるフレイレとのデュオ、そして小澤征爾指揮の新日フィルとのチャイコン協演。どれも見逃せない。アルゲリッチの成熟とは、安定ではなく、多様性への挑戦と深まりにあった。
鬼、と言ってはその紳士的風貌にそぐわないが、編集部が取材し起こした原稿を素早くリライトし整えて最終的な記事に仕上げるアンカーマンが、岩崎呉夫氏(注1)だった。眼光鋭く、セブンスターを吸いながら、パーカー万年筆で隷書体のような美しい文字をさらさらとペラ(200字)原稿用紙に走らせ、それを3分に一度ピッと引きちぎり、アッという間に記事を完成させる。時々貧乏ゆすりしながら、「次の原稿は、まだ?」と私たちを催促する。超人的スピードで仕上げる膨大な記事の質量に、誰もが舌を巻いた。
「岩崎は昔からこうだったよ」と編集長の内藤克洋(1927~2018)は語る。ことあるごとに助っ人として飛んできて、内藤社長を支えてくれる古くからの不思議な友人。岩崎氏は『ショパン』創刊から1年半の間、デスクとして喝を入れてくれた。
「アルゲリッチの魅力の真髄は? 3つ挙げよ」と鬼デスクの声が飛ぶ。来日予告の記事に見出しを付けるのだ。「華麗!」「多彩!」「パッショネート!」と応えると、「ハハハ確かに。だけどアルゲリッチは他の女性ピアニストとは違う。もっと独自の美質は?」と追及される。
う~ん、と言葉に詰まって、「インスピレーション」、「冴えわたる鋭い感覚」、「情熱の奔流」、「ダイナミックなエネルギーの爆発」…やっと挙げれば、「ウン、どれもそうだが、何か足りないな」。「テンペラメントはどうだろう」とデスクは言った。temperamentすなわち一瞬ごとに揺れ動く激しい起伏をともなう感情、そんな振幅のある気質。そうかもしれない。でも少々馴染みのない言い方では? 編集部は自信がなかった。
84年10月、ついにアルゲリッチが来日。昭和女子大人見記念講堂でのリサイタル。生身のアルゲリッチが登場するや、その凄絶な美しさに息をのんだ。
シューマン「クライスレリアーナ」の演奏で、夢のように繰り返されるエネルギーの凝縮と発散、フロレスタンとオイゼビウスが交錯し、湧きおこる感情の激しい振幅に翻弄され続けた。岩崎デスクの見立ては的中した。まさに生(なま)の「テンペラメントな」揺れ動く演奏だった。
音楽家は音楽表現で勝負するのだから、感性と技術が大事で、舌足らずな言葉は要らない、ということはない。同じく音楽家を紹介する雑誌作りでは、言葉を磨くことが求められた。特に見出しとキャプションには細心の意を用いるよう岩崎デスクは根気よく若輩を手ほどきしてくれた。しかし未熟な編集部が一朝一夕にできるわけがなかった。言葉を知らない、想像力に欠ける、思いやりが足りない。
創刊3号で、ドイツで長らく活動している杉谷昭子氏が、日本でブラームス・ピアノ曲の全曲録音に挑んでいる、そのレコーディング現場を取材した。ドイツの暗いうっそうとした寒い森をイメージしていた私に、杉谷氏は明るく楽しく、おおらかに接してくださった。人を包み込む大きく居心地のよい温かさ。帰社後このことを岩崎デスクに報告すると、一言「それはゲミュートリッヒカイトだ」と応えた。Gemütlichkeit、初めて聞く言葉だ。日本語ではぴったりする言葉がないが、杉谷昭子氏のおおらかさは、このニュアンスに間違いなかった。 …それにしても博覧強記の岩崎デスク。
内藤社長も岩崎デスクもヘビースモーカー。社長室の壁は、長年のヤニで黄色く染まっていた。ここで二人がする会話が編集部に漏れ聞こえてくる。
創刊号のプレゼントにした坂本龍一のカセットブック「アベックピアノ」の「戦メリ」を聴きながら、内藤社長が「何だこの音楽、繰り返しばっかじゃないか。クライマックスがない」と言うと、「おい内藤、音楽の根源は、レペティション(繰り返し)とヴァリエーション(変化・変奏)にあるんだ、これが原点だとシェーンベルクが言ってるぞ」と岩崎氏。そして「そもそも生きるということが、繰り返しと変奏の連続じゃないか。クライマックスを求めるな。雑誌の発行も同様だ」と。ハッと我に返り慌ててメモを取る編集部。日常のささやかなレペティションとバリエーションに注意を注げ、派手さにとらわれるな、と岩崎デスクに教わったのだった。
(注1)
岩崎呉夫氏(1925~1993)の本質は詩人だった。とりわけ著書『詩集1』(1969年 若い人社文学会)に刻印された‘人間詩’が力強い。
同時に評伝作家として、3つの代表作『芸術餓鬼 岡本かの子伝』(1962)、『炎の女 伊藤野枝伝』(1963)、『燃えて走れ "伝説"のレーサー浮谷東次郎』(1972年)で、無名の3人を発掘し、その生命力を苛烈に描いた。
後に『かの子繚乱』と『美は乱調にあり』を著して一躍有名になった瀬戸内晴美(寂聴)氏は、「岩崎呉夫の丹念で地道な掘り起こしがなければ、私のかの子と野枝の作品は生まれていない。彼の著作を原資料として、私はその上をブルドーザーで突っ走ったようなものだった」と述懐し記している。また『JIN-仁』や『龍-RON』で知られる村上もとか氏は、岩崎呉夫の『燃えて走れ』を原作としてマンガ家デビューを果たした(集英社『週刊少年ジャンプ』連載)。
編集者&ライターとしては、文藝春秋社、講談社、プレジデント社で、武道家、芸術家、宗教家、実業家たちの著作の構成執筆に携わり、多数の書籍を作った。
『ショパン』ではデスクとして、これらの人間学的視点をベースに編集部を啓発してくれた。