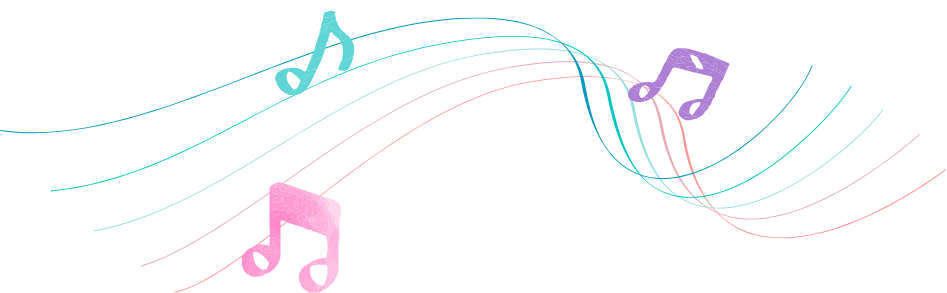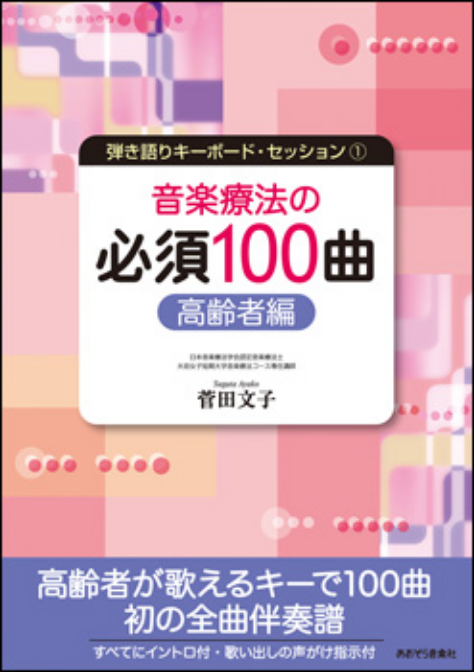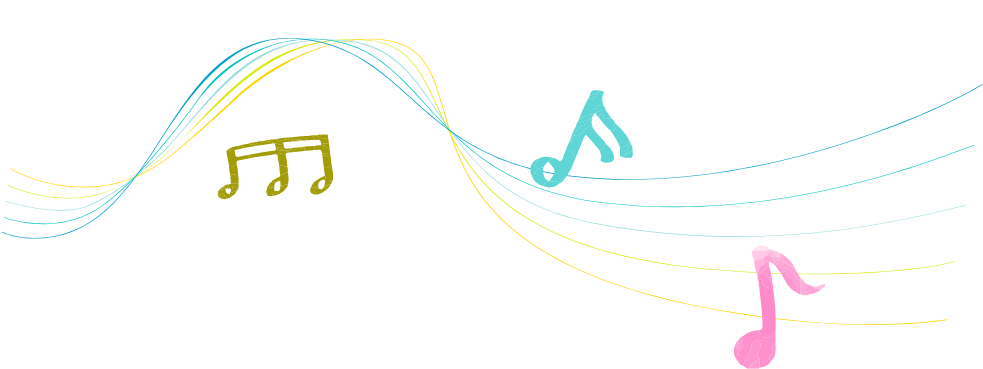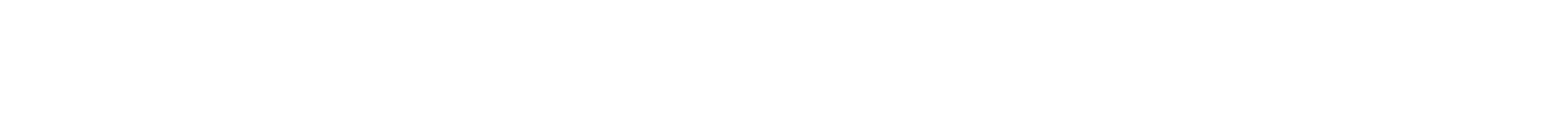新型コロナ禍での音楽療法・対面セッション

- 菅田文子 (大垣女子短期大学・音楽療法コース教授)
制限下でも達成できることは多い
「コロナ禍における対面音楽療法」で留意すべき点はさまざまありますが、セッションで厳守する必須事項として次の点を優先する必要があるでしょう。
- 飛沫を飛ばさない
- 自分以外の身体に触れない
- 楽器や小物を自分以外の人に回さない
- 対象者(参加者)との空間的距離をとる
- 指示伝達の工夫(マスク下での発声・滑舌と、表情・アクションを明瞭に)
- そのうえで相互の意思疎通とコミュニケーションの確立をめざす

上記をふまえ「(至近距離で)歌わない」、「楽器を使い回さない」ことを条件とした場合でも、工夫次第で音楽療法の目的の多数を達成できます。
- 音楽に合わせた運動機能の維持向上
- 息が上がるような激しい運動ではなく、グーチョキパーを作る、指を順番に折るなどの活動も考えられます。
- 音楽に合わせた口腔機能の維持向上
- 声を出して歌わなくても、口を大きく開ける、意識して形作ることで口筋を動かすことができます。
- 音楽を使った言語機能の維持向上
- 音楽のリズムやメロディーの抑揚に合わせることで歌詞や言葉がスッと出てきます。
- 音楽を使った認知機能の維持向上
- 判断力、記憶力、観察力、集中力、注意分配力、回想を促すことができます。
- 音楽による情動調整・情動発散
- 楽器を持って音に合わせて鳴らすことで発散することができます。
- 音楽を使った達成感・他者認知・参加意欲・一体感etc.の獲得
- 声を合わせて歌うことができなくても一緒に楽器を鳴らしたり音楽に合わせた動作を行うことによって達成感や一体感などを感じることができます。
そのような一例として、大垣女子短期大学・音楽療法コースで行っている現場実習でのセッションをご紹介します。
新型コロナウイルスの影響により、施設実習、特に高齢者施設における実践は2020年から中止となっていました。しかし昨今、施設利用者や職員がワクチン接種済みとなったことから、本学卒業生が勤務する施設より、久しぶりに音楽活動を行いたいという連絡があり、次のような趣旨による下記の内容(表参照)を特別養護老人ホームで行いました。
利用者(入所者)と職員の皆さんはワクチンを接種しているとはいえ、教員、学生とも未接種であることや、通いのデイサービス利用者には未接種の方も含まれるという理由 で、従来のプログラムとは異なる内容を求められました。現在も続く新型コロナ禍において今後も考慮しなければならないことと考えます。決してベストな内容ではないと思いますが、こういう形もできたという一例です。
施設の外部から人を呼ぶのは1年半ぶりということで、スタッフが積極的に利用者を招いた結果、参加者が60名余という大きな集まりとなりました。こうした大きなグループを対象とする1回限りの活動は、音楽療法と銘打つにはイベント的な大規模なものになりがちですが、その中でも利用者の認知機能に合わせた活動を提供するように心がけました。
活動プログラムは下表のとおりで、あらかじめ施設に伝え了承を得ました。
歌唱は避けたいということでしたので、楽器活動や身体活動、鑑賞が主のプログラムとなりました。鑑賞については本学学生が障がい者施設で実践を行ったときの曲目を用いたため、年代的にやや若めの選曲となっているかもしれません。
対面での音楽療法セッション (令和3年7月21日実施)
注意点:対象者は歌わないようにする。ガイドとしてスタッフが声出しすることはある。
| 活動 |
目的 |
備考 |
|
1.海(松原遠く)
『必須100曲 高齢者編p.66』
歌詞を(発声はせず)口を動かしながら無音で歌う
|
口の動きに意識を向ける |
マスクを外し、アクリル板を挟んで口パクでお手本を示す |
|
2.三百六十五歩のマーチ
『必須100曲 高齢者編p.210』
座位のまま上肢を動かす。一部、足踏みあり。
|
上肢の動きを促す
下記説明イラストを参照 |
|
|
3.うみ(うみはひろいな)
『必須100曲 高齢者編p.65』
メロディーのフレーズごとの声かけを聞いて、相手に勝つように「後出しじゃんけん」を行う
|
デュアルタスク(異なるさまざまな能力を同時に使う)。
1曲を通じて、聴覚、視覚、注意切替、観察力、判断力、集中力を刺激する |
|
|
4.ソーラン節
『必須100曲 高齢者編p.70』
「ハイ、ハイ」でリズムをそろえて鳴らす
|
声が出せなくとも思い切り音を出すことによる発散、リズムを合わせることによる認知機能の促進 |
楽器配布
(鳴子、鈴など) |
|
5.ミニコンサート
1. アイネクライネナハトムジーク
2. 小さな世界
3. Let it Go
4. 海の声
5. 世界に一つだけの花
|
リラックスして生の音を楽しむ |
楽器を手元に置いたまま鑑賞。
テンポの良い曲では楽器を鳴らして参加していただく
楽器回収
|
|
6.瀬戸の花嫁
『必須100曲 高齢者編p.196』
小声で口ずさみながら、四拍子の指揮の動きをする
|
歌いながら、上肢で指揮の動作の模倣。デュアルタスクによる聴覚、発声、記憶力、視覚、観察力、注意力、上肢筋力の同時刺激と覚醒 |
|
教員と学生は1週間前から検温し、行動記録をつけます(当日回収、コピーを取って返却)
三百六十五歩のマーチ 動作
-
イントロは手拍子
-
「幸せは歩いてこな い、だから歩いてゆくんだね」のフレーズは、グーに握った右手を2拍ごとに動かします。「幸せ」で胸の前、「はー」の2拍で前に出す、「歩いて」で胸の前、「こない」で前に出す。右手グーを(胸→前)×4回です。次は左手に替え、「一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩さがる」で同様に、左手グーを(胸→前)×4回です。
-
「人生はワンツー パンチ、汗かきべそかき歩こうよ」では2拍ごとに左右交互にグーを突き 出します。(右手グーを前、左手グーを前)×4回です。
-
「あなたのつけた足跡にゃ きれいな花が咲くでしょう」では、2拍ごとに両手グーを同時に前に出し、ひっこめます。両手グーを(前→胸)×4回です
-
「腕を振って足を上げてワンツー、ワンツー、休まないで歩け」では腕を振り足踏みします。
-
「それワンツー、ワンツー」ではイントロと同様に手拍子します。
腕を前に出し、横(左右)に出さないので車いすが並んでいてもぶつかることなく、無理なく動かすことができます。児童デイサービスに勤務しながら学んでいる社会人学生が考案してくれました。
うみ デュアルタスク
方法:後出しじゃんけんの要領です。最初に音楽療法士が「私に勝ってください」と指示を出し、「うみはひろいな、大きいな」と歌って一度止めて「じゃんけん、ぽん」と言いながら先に出します。
参加者は音楽療法士を見て、それに勝つように手を出します。難しいようならば「ハサミに勝つのは何ですか」とヒントを出します。
全員が手を出したのを確認してから次のフレーズ「月は昇るし、日は沈む」と歌って止めて、再度じゃんけんします。
これが簡単にできるようならば、次は同じ後出しの要領で「今度は私に負けてください」というバージョンも行います。(今回はそこまで進めませんでした。)
ミニコンサートの様子。キーボード3人連弾による「アイネクライネナハトムジーク」。
「鑑賞」の時間ですが、「参加型」とします。数十分の間、ただ聴くだけではソワソワし出しがちな利用者の方々も、鳴子や鈴などを手にすると、気分に応じて、リズムに合わせて、または興が乗った時に自然に鳴らすことで、落ち着いてその場にいることができるようでした。
ミニコンサートの様子。キーボード連弾とアコーディオンによる「小さな世界」。
手拍子のできない片麻痺のある人も、鳴子でリズムに合わせた音楽活動ができます。
活動を終えて
高齢者施設で活動をさせていただけたのは1年半ぶりで、今回初めて高齢者施設に入るという2年生の学生たちと一緒に行いました。歌唱は行わない原則のため、歌に入る前の誘導の声かけなどは行いませんでしたが、参加者の方々が自然に小さく口ずさんでしまうのは仕方ないかな、という施設の意向も聞いていましたので、絶対に発声禁止という形ではありませんでした。ただし、マスクを外したり、ずらしている方には施設スタッフがすぐに声をかけてサポートしました。
認知機能が低下している方も多いとあらかじめ聞いていましたが、実際には目の前のお手本を見て動きや鳴らし方を模倣する活動はスムーズに行うことができました。歌いながらじゃんけんをするというデュアルタスクは困難な方が散見されましたので、もし継続してセッションを行うのならば、「簡単にできて楽しめる活動」と「注意や努力が必要な活動」を意識してバランスよく取り入れてゆければと思いました。
参加した利用者の皆さんは大変喜ばれ、終了後に私たちが移動する間も声をかけてくださいました。
施設からは、(今回は60名以上の会場でしたが)後期からは小規模なユニットでも活動してもらいたいと要望をいただいていますので、工夫と配慮を重ねながら少しずつ音楽活動を再開していきたいと考えています。
(すがた・あやこ)
「音楽療法」は予防医学と在宅医療でも必要とされ始めています
音楽療法とは「音楽や音のもつ生理的・心理的・社会的な機能を活かし、治療的に利用することで、心身の回復、健康維持などを促進する活動全体をいう」とされています。
医療・福祉・保健・教育等の各分野でここ数年、急速な勢いで実践者が増えつつある「音楽の新しい専門ジャンル」です。
すでに病院やホスピス、リハビリ施設、福祉施設、教育現場等で実践されています。ところが、昨今のように新たな社会問題が深刻化する中、音楽療法を必要とする対象者は、従来の病気や障害を持った人だけではなく、一般の健常者へと広まりつつあります。
何よりも、急速な高齢化社会の到来、家庭介護の増加、職場の人間関係・テクノストレスが引き起こす精神神経障害の増加、長期化する不況と中高年の失職、大学卒業生の就職難、100万人とも言われる子どもから大人までの引きこもり、不登校、青少年の犯罪の増加、年間3万人に及ぶ自殺者など、こうした環境下では、誰もがいつ病気になってもおかしくない状態と言えましょう。音楽療法は、まさにこうした内面の危機を抱えた人々にこそ、効力をもつ「補完医療」と言えます。
今後ますます予防医学としての健康促進活動が必須となりますが、音楽療法は、人間の「五感」すべてを使う全身・全感覚の機能改善法として、他の芸術療法にはない「強み」をもっています。音楽系大学など専門教育機関での「音楽療法コース」の開設が増える一方、各自治体で独自の音楽療法士の資格認定を行うなど、音楽療法はますます社会に必要とされるジャンルとなっています。そして今後急増するであろう「在宅医療」の中に音楽療法を活用する試みにも大きな注目が注がれています。
◆現在の音楽療法の現場をウォッチングする中から感じたこと・考えてゆきたいことをまとめたのが次のページです。あおぞら音楽社としての考え方が書かれています。雑誌『現代のエスプリ』に所収されたものですが、許可を得て掲載しました。
『現代のエスプリ 424号』 音楽と癒し-音楽療法の可能性 p.198~205 (至文堂 2002年10月)所収
これからの音楽人に必要な音楽療法の技

- 北島京子(『イキイキ音楽療法のしごと場』編集発行人・あおぞら音楽社代表取締役)
気になる現象1
…お年寄りの「不登デイ」
ある高齢者施設のデイサービス担当の職員の話である。
「最近、気がついたのだけど、決まった曜日になると、決まってデイを休む人が、何人かいるのよ。よくよく調べてみると、それは音楽療法のある曜日だということがわかったの。ご家族の人にうかがったところ、『おじいちゃん、きょうは音楽をやらされるから行かないって、布団をかぶったまま起きてこないんですよ』とおっしゃるじゃありませんか。施設としても音楽は人気メニューだと信じて、音楽療法を導入しているんですけど…」。
ショックな話である。小中学生たちの「不登校」ならぬ、お年寄りの「不登デイ」。そしてデイに行かないその理由が、「音楽療法」にあるとは。
その通所者にとって「音楽をやらされる」ということが、ほとんど「いじめ」に近いものに感じられるのか、「無気力」を引き起こす原因になっているのか、どちらかなのだろう。
また、ある医療職の人は、こう話した。
「しっかりしたご老人の方ですが、こうおっしゃるんです。『また鈴を振らされるかと思うと、もう…。頼むからあの時間には、誘わないでくれ。そして私がこの先、もしも呆けて自分で判断がつかない状態になっても、あれ(音楽療法)だけはやらさないでくれ』って。私が笑って聞き流しますと、ご本人は真剣になって『本気ですよ、遺書にしたためますから』とまで言い出すんです。笑いごとではありません…」。
さらにショックである。このご老人にとって自分のプライドにかけても守りたいものが、音楽療法に参加しないという意志なのである。この人をここまで頑なにさせてしまったものは何なのだろう。単なるガンコ老人の好き嫌いのレベルではない、もっと本質的な原因が、音楽療法を提供する側にひそんでいるのではないだろうか。
音楽療法は「誰のためのものか」を、改めて考えてみる必要がある。言うまでもなく患者さんをはじめとする、病気や障害、弱い部分をもった「対象者」が主人公、音楽療法士はその支援者であると、誰もが答えるだろう。
しかし現実は、本当に音楽療法を受ける側すなわち「対象者」のニーズと、音楽療法を見守る側すなわち「対象者のご家族や、対象者を受け容れている各病院や施設の職員たち」のニーズに応えた内容になっているだろうか。
気になる現象2
…供給側の人数は、なぜ増える?
音楽療法を実践する人はさまざまな領域(医療・福祉関係)に身を置く人も多い。が、なかでも町のピアノの先生や音楽教室の指導者など、これまで音楽教育に携わってきた人々が圧倒的に多いのが特徴と言える。
これはなぜだろうか。「近年の少子化で子どもの生徒が減ってしまい、時間が余り、減収となった。そこで、音楽療法の世界に活路を求めて」という動機を強調する人が多い。もちろんこれもある。が、これだけではない。それ以上に「音楽療法へ」と彼らを突き動かす何か強い要因があるように感じられる。
子どもの頃から一生懸命音楽を学んできたが、どうもその音楽で幸せになれないと感じた時に、音楽をする意味を自分で問わない人はいないはずである。音楽療法に注目する人の中に、これまで自分の受けてきた音楽教育に必ずしも誇りを持っていない、逆に、懐疑や悔恨さえ抱いている人が多いことが、気になる第二の点である。
人と人を結びつけ、人を幸福に導くはずの音楽が、そのように働かず、技術偏重主義・競争主義・教条(権威)主義の音楽教育の中で、逆に人をバラバラにしてきてしまった。さらに、コンクール指向や受験教育による点数還元主義は、成長期の子どもの心身のバランス良い音楽的発達や柔軟な音楽的感受性の芽を摘んでしまうことを実感してこなかった人は稀だと思う。
そんな時「音楽療法」のことばが、魅力に満ちたものとして登場する。自分自身が受けた音楽教育への懐疑とともに、それへのアンチテーゼとして「音楽療法」に着目した人は多い。「音楽をする意味」を、音楽療法の中でもう一度、問い直したい、音楽療法を通して「自分探し」をしたい、という切実な動機があるように思われる。こうした人は今後も増えるはずだ。
近年の音楽療法の実践をになう人に、音楽教育に携わってきた層が多いことの意味を、もっと深く考えるべきではないかと思う。
気になる現象3
…潜在需要層も増えてはいるが
平成14年の「敬老の日」の発表(総務省統計局)によれば、日本人の18.5パーセントが65歳以上、つまり「5.4人に1人が、65歳以上」となり、75歳以上の人口が初めて1,000万人を突破したという。超高齢化社会がいよいよ現実になってきている。
西洋近代医学の発展によって、確かに、心臓停止までの命の長さLOL (レンクス・オブ・ライフ)は達成された。が、それは、人間としての命の質QOL(クオリティ・オブ・ライフ)も達成されたこととイコールではない。逆に命長ければ苦しみも多いのが現実である。自殺者の数が年間3万人を越えるようになったことも、気になる。
かつて「病気」ならば、医者に診てもらって治療し、治れば「元気」になった。「病気」と「元気」の二元論で割り切れた。しかし、現代は「病気」と「元気」のあいだの黒でも白でもないグレイのゾーンが多く存在することになった。例えば、慢性疾患、免疫系の病気、身体の障害、心の病、老化など。これらは、新薬や手術では治せない。
つまりこれからは、「急性期の治療(キュア)」に対して、「慢性期の養生と介護(ケア)」に費やす期間がますます増大することになる。
こういう時代に音楽療法はどういう力を発揮できるのか? どんな役割が期待されているのか?
そんな時「音楽療法」のことばが、魅力に満ちたものとして登場する。自分自身が受けた音楽教育への懐疑とともに、それへのアンチテーゼとして「音楽療法」に着目した人は多い。「音楽をする意味」を、音楽療法の中でもう一度、問い直したい、音楽療法を通して「自分探し」をしたい、という切実な動機があるように思われる。こうした人は今後も増えるはずだ。
近年の音楽療法の実践をになう人に、音楽教育に携わってきた層が多いことの意味を、もっと深く考えるべきではないかと思う。
代替医療の一環としての位置づけを
西洋近代医学は「急性期の治療」を得意としたが、「慢性期」の状態に対しては歯が立たないことが多い。
これからは人間の「生老病死」まるごとといかにつきあっていくかを取り込んだ医療への模索を、避けて通るわけにはいかなくなってきているのである。医療は「病の治療」だけではなく、人間の「命」や「心」に目を向けていかなければ成り立たなくなりつつある。
ところが、生命はもともと「複雑系」である。機械のように切り刻んで悪いところを取り除いて再び「合成」しても、もとの「全体」には戻らない。ある細胞をめがけてレーザー照射しても、健康な組織まで一緒に殺してしまうという副作用が大きすぎた。
これからは「全体性」や「部分と部分のつながり」を、無視できなくなるだろう。「命」や「心」は、「全体性」からしか眺めることができず、部分と部分の「つながり」が意味あるものなので、西洋近代医学が得意とした細分化や合成の論理では説明できないのである。
通常の西洋医学を補う代替療法(オルタネイティブ・メディスン)、補完療法(コンプリメンタリ・メディスン)の各種療法の中には、生命の全体性やつながりを重視するものが多い。医学全体が、人間まるごとを見るホリスティック医学の視点に立ち始め、市民権を得つつある。そうした流れが、アメリカから伝わってくる。
日本の厚生労働省にあたるアメリカのNIH(国立保健研究所)内に、正式に「代替医療研究室」が開設されたのは10年前である。また、アメリカの半数以上の医大では、代替療法を学ぶ学科が設けられている。さらにアメリカ人の医療保険費が、通常の西洋医学に支払った金額よりも、代替医療に費やした金額のほうが上回っていることも興味深い。
西欧近代の知をもって西洋医学がここまで進歩したお陰で、その限界を越え、ホリスティック医学への重要性にめざめつつあるようだ。こうした価値観の転換期、時代の過渡期に生まれ合わせたことは、ありがたいことだ。
と同時に、音楽療法こそ、西洋医学を補う代替医療の一環として「ホリスティックに人間を考える」という文脈から出発することが望ましい。でないと、音楽療法はEBM(evidence based medicine 科学的根拠に基づいた医学)への数値とデータだけが一人歩きするあやしげな療法と受け止められかねない。
音楽が、ある臓器を治すことはないし、音楽と治癒との因果関係や効果の持続性、再現性は数値にはなりにくい。なぜならば、音楽は対象者とその人を取り巻く「場」の全体に働きかけ、人と人とのつながりに何かを生じせしめるものだからである。このことが前提である。
「EBM」の裏付けをもった西洋医学で「身体」は治せても、「心」は癒せない。だから、音楽療法に意味があるのである。
供給する側の論理
以上の「3つの気になること」を総合してみると、自然に導かれる問題がある。
昨今の音楽療法が、受ける側よりも「供給する側の論理」優先で進められていないだろうか、という点である。
音楽療法を実践したいという人は多い。が実践場所がないという声をきく。本当にそうだろうか。
高齢者のための各種施設およびさまざまな障害者施設、養護施設などが、現在国内に約1万8,000箇所ある。(ここ数年のうちにさらに増え続ける傾向にある)。これらは音楽療法の貴重な実践場所である。
それに対して全日本音楽療法連盟(日本音楽療法学会)が認定した音楽療法士の資格保有者は平成14年現在、580人余。資格の有無に関係なく現在、施設での音楽活動に携わっていると推測される総数は、およそ3,000人程度。数の上では「実践現場が足りない」状況ではない。だが実際には「実践現場が足りない」と言われる。
ひょっとすると「押しかけ音楽ボランティア」に辟易した施設側から「ノーサンキュー」が言い渡され、実践者は締め出しをくらっているケースもあるのだろうか、という不安もよぎる。
受ける側のホンネ
では、受ける側は、どのような音楽療法ならば安心でき、満足できるのだろうか。
それには、仮に自分が「音楽療法を受ける側になった場合」を想像してみることだ。
・緊張したくない、気分をラクにしたい、心のマッサージをしてほしい
・むずかしいことはいや、楽しみたい。新しいことに挑戦させられるのも辛い
・自分の好きな音楽や、馴染みの歌があれば嬉しい
・ドキドキわくわくしたり、気分転換の助けになればいい
・おしゃべりや気軽な質問ができる雰囲気がほしい
・ただ、聴いて黙って座っているだけの参加も認めてほしい
・フラッと立ち寄れたり、参加しない自由も認めてほしい
この程度のことが多いはずである。それほど高度なことを受ける側は期待しているわけではない。まず「自分が受ける側だったら」の立場に立ち、「やってほしくないこと」を消去していく。結果的に「たいしたことではないこと」「当たり前のこと」が残ってくるが、ここに挙げたことすべてを肩に力を入れずに行うのは、「初歩の実践者」には結構大変なことである。
現場で必要な力と技
音楽療法の実践者にはその場ですぐに取り出せる「音楽の貯金」が多ければ多いほどよい。しかも、その貯金をその国の「通貨」で取り出せることが必要である。対象者が好む音楽、リクエストする音楽のストックを、対象者の生活してきた音楽文化にピント合わせて提供できなければ意味がない。
青江三奈の「伊勢佐木町ブルース」を、ソプラノの完璧なコールユーブンゲン的ソルフェージュで唄っても、対象者には別の歌に聞こえることだろう。歌には、香りや色がある。その人が育ってきた時代・環境・嗜好がそこににじみ出る。音楽大学や教室では教えてくれないが、現場では必須の要素である。
対象者のために即興で伴奏でき、即興で曲を演奏できなければいけない、とよく言われる。
即興の技術に関して言えば、先進国のある種の規範やお手本を理解してなぞる力よりも、現場の空気を読みとり必要に応じて同化できる身体感覚と、限られた簡単な音を使って問答できる創意工夫性のほうが、より大事と思われる。伴奏力は、和声づけ以上に、対象者の呼吸とテンポに同調できる「気」の読みとり力が求められる。
音楽療法は理屈ではない。音楽は「感性言語」であるため、感覚や感情にふれるものである。対象者が、まず音を楽しむことができ、「いい気持ち」を実感できなければ、どんなに立派な理論や目標が用意されていても、活きない。音楽を楽しむ、満足する。これが出発点である。
カロリー計算上や栄養学的にいくら完璧な数値を示していても、「だ液」が少しも分泌されないで食べる食べ物は身にならない。音楽療法は、栄養学の知識よりも、あり合わせの素材でいかに美味しい料理を作れるかが勝負である。管理栄養士の「頭」ではなく、現場の料理人の「腕」が求められる世界である。
音楽療法の勉強は、技術主義、競争主義、点数主義とは正反対の側にゴールがある。
演奏技術のレベルが問われるのではなく、現場での応用力のレベルが問われるのである。また、人よりいかに抜きん出るかではなく、人からいかに信頼され慕われるかである。そして、点数で表せば大事なものがこぼれ落ちる代わりに、五感を総動員して接すれば何かが伝わり、何かが返ってくるのが実感できる、誠にデリケートなセンサーで評価される世界である。
音楽療法の最も正直な審査員は、目の前の対象者である。対象者の目をいかに輝かせられるか。これが音楽療法の成績表である。
隣接分野との連携
また、これからの現場で重視されることになるものに「チーム・アプローチ」がある。留意しなければならないことに、音楽療法が独自で力を発揮することもあるが、多くは、さまざまな他の職種と連携しリンクし合って、複数の力が掛け合わされた結果、相乗効果としての成果が認められるのである。その場合も、音楽療法の実践者はそれを一人の力によるものだと錯覚しがちなケースが、ままあることである。
作業療法士や理学療法士、言語聴覚士、臨床心理士をはじめ、介護士、看護師、施設職員など、複数の職種の人たちと共通言語で話しができる視野と知識と経験を身につけていかなければ、音楽療法は現場から取り残されてしまうおそれがある。音楽を専門に学んだ人は、感性が豊かな割に、一般の人に通じる言語ボキャブラリーが乏しいことを自戒せねばならない。
音楽独自の力
しかし、独りの力で大きな世界を創り上げている音楽療法家もいる。最後にその一人を挙げておきたい。
丹野修一という作曲家である。精神分裂病(統合失調症)の患者さんたちが一緒に参加する、独自の即興合奏療法を編みだし実践し続けて三十数年。その音楽は、膨大な数にのぼる。同じ曲でも聴くたびに、その合奏の参加メンバーによって、その場の空気によって、毎回違う音楽となって聞こえる。
これらの音楽にふれてまず直感することは、「自然界」から何らかの啓示とインスピレーションを受けているのだろうということだ。水や風や光や大気の揺れに始まって、星のきらめきや季節のめぐり、潮の満ち引きを思わせる大きな「循環」。単なるパターンミュージックの機械模様ではない、果てしなく続く流転と揺らぎから生まれる音のアラベスク。温かさや湿り気、でこぼこの手ざわりの中に、不思議な調和感が得られる。
「倍音」の多用も特徴のひとつと思われる。それが不思議な共鳴をもたらす。
そしてこれらさまざまな要素を「統合」させるのは、丹野氏の指揮の「呼吸」である。
丹野氏の音楽は、これからの「音楽療法の音楽」研究のカギを握る大いなる示唆を存分に含んでいるはずだと確信する。